 Healthy Food
Healthy Food 紫蘇を入れて、真っ赤な梅干しを作ります
さて、そろそろ店頭からも青梅が消えてきました。梅仕事は、6月上旬には、してしまわないと材料がなくなってしまいます。 いよいよ漬けた青梅に紫蘇をいれて、長期保存の梅干しをつくります。 最近は、梅干し用の紫蘇は、梅酢とセットになってパックで売っ...
 Healthy Food
Healthy Food  Healthy Food
Healthy Food  Healthy Food
Healthy Food  Healthy Food
Healthy Food 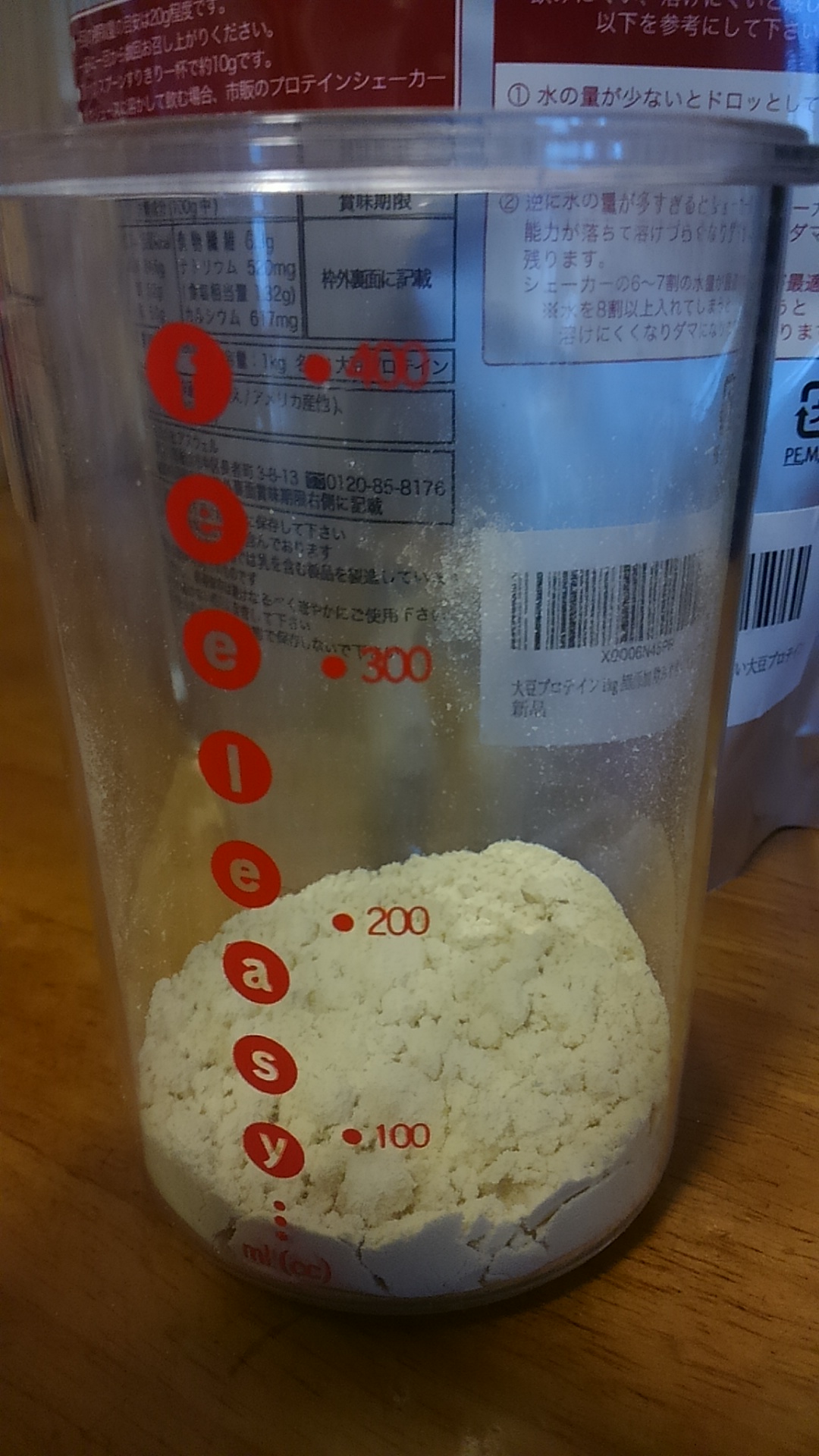 Healthy Food
Healthy Food  Healthy Food
Healthy Food  Healthy Food
Healthy Food  Healthy Food
Healthy Food  Healthy Food
Healthy Food  Healthy Food
Healthy Food