 Yoga&Healthy muscle
Yoga&Healthy muscle 筋トレ最強です! 精神を強くしてくれる最強ツール
皆さんお久しぶりです♪ 教室をやめてしまって、9か月くらいになります(^^;) このブログも更新が止まってしまって、いま慌てて書いていますwww まずヨガについての近況報告♡ ヨガの指導力が落ちないように毎日トレーニングは続けています♪ (...
 Yoga&Healthy muscle
Yoga&Healthy muscle  Yoga&Healthy muscle
Yoga&Healthy muscle 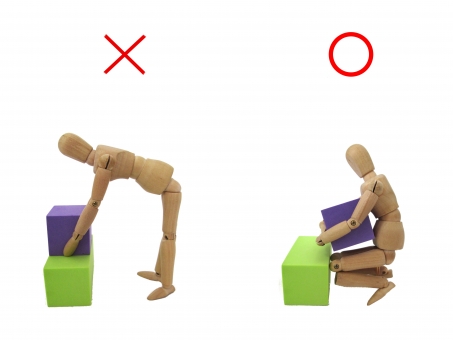 Yoga&Healthy muscle
Yoga&Healthy muscle 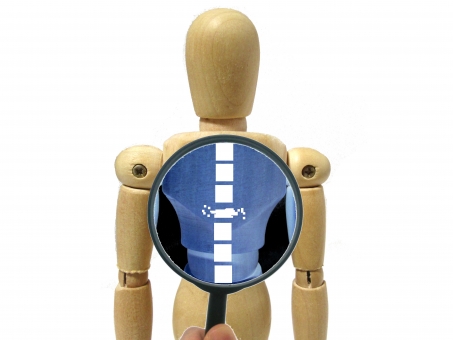 Yoga&Healthy muscle
Yoga&Healthy muscle  Yoga&Healthy muscle
Yoga&Healthy muscle 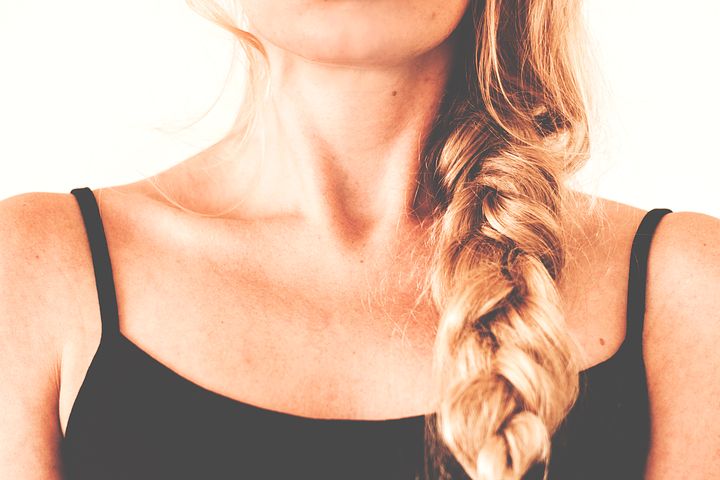 Yoga&Healthy muscle
Yoga&Healthy muscle  Yoga&Healthy muscle
Yoga&Healthy muscle  Yoga&Healthy muscle
Yoga&Healthy muscle  Yoga&Healthy muscle
Yoga&Healthy muscle  Yoga&Healthy muscle
Yoga&Healthy muscle